ツィッターでは既に周知してるけど、いま海外出張中なのでこのブログの更新ができてません。ネット環境とかは整ってるんだけど、朝から晩まで忙しくて自分の時間がないんよ。
来週以降にまた更新開始します。
ツィッターでは既に周知してるけど、いま海外出張中なのでこのブログの更新ができてません。ネット環境とかは整ってるんだけど、朝から晩まで忙しくて自分の時間がないんよ。
来週以降にまた更新開始します。

なんか不思議な時期に始まったフォックスのTVシリーズ。基本的にはアクション・コメディで、露骨に80年代の刑事ドラマのパスティーシュになっている。
主演の刑事2人組を演じるのは、トムの息子ことコリン・ハンクスと「ザ・ホワイトハウス」のブラッドリー・ウィットフォード。前者はドジだけどもっと真剣な事件を扱いたがっている若手刑事で、後者は25年前に知事の息子を救出したことで一躍有名になってものの、今は飲んだくれで時代遅れになっている刑事という設定。この凸凹コンビが組んで事件を解決していく内容になってるんだけど、2人の行動に手を焼く上司とかも含め、過去の刑事ドラマの焼き直しという感は否めない。
本国ではビースティ・ボーイズの「サボタージュ」のPVのドラマ版なんて言われているようだけど、まあこの古くささをどうやって面白さに昇華させるかが今後の課題だろうな。第1話を観た限りではマヌケなメキシコのカルテルの一味や、臆病だけど口の達者な黒人の質屋とか、人種のステロタイプな扱いが見受けられるのも気になる。あと捜査が行ったり来たりしているというか、なんか話のテンポが悪いんだよね。この話を監督したティム・マシソン(「ザ・ホワイトハウス」の副大統領だよ)はアクション系の番組を撮るのは巧くて、ここでも最後のカーチェイスなんかはよく撮れてるんだけど、コメディには向いてないような。さらに言うとウィットフォードもコメディ向きではないじゃないの。「Studio 60 On The Sunset Strip」とかのほうがずっといい演技してたぞ。
本国での評判もイマイチのようなので、早急にパロディとドラマの正しいバランスを見つけないとあまり長続きしないのでは?昔の刑事ドラマへのオマージュという意味では「ライフ・オン・マーズ」のほうが100倍くらい面白かったぞ。
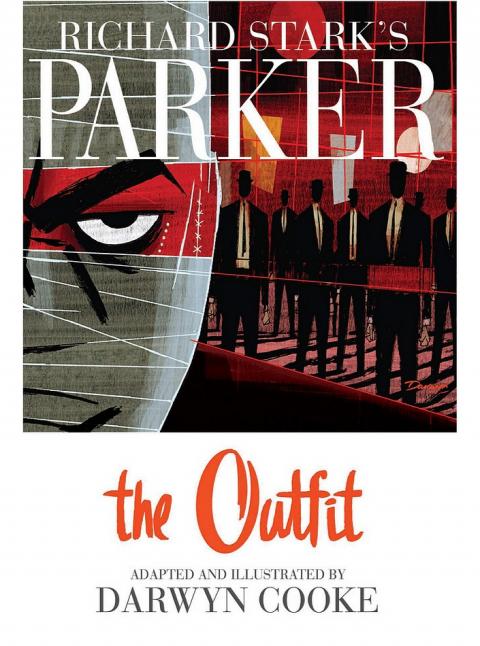
リチャード・スタークの犯罪小説「悪党パーカー」シリーズを原作にしたダーウィン・クックのコミック第2弾「The Outfit」のプレビューが公開されていた。
俺が知る限りこれはシリーズ第3作を原作にしたもので、クックは以前に語っていたとおり第2作目の「THE MAN WITH THE GETAWAY FACE」は割愛することにしたのかな。今回の主人公パーカーは整形手術をして新しい顔を得たという設定なので、第1作と主役の顔が変わっているというのがコミックでは特に強調されて奇妙な感じがするね。個人的に前作は必ずしも満点の出来ではなかったけど、ダーウィン・クックは非常に好きな作家なのでこれもいずれ買うことになるかな。
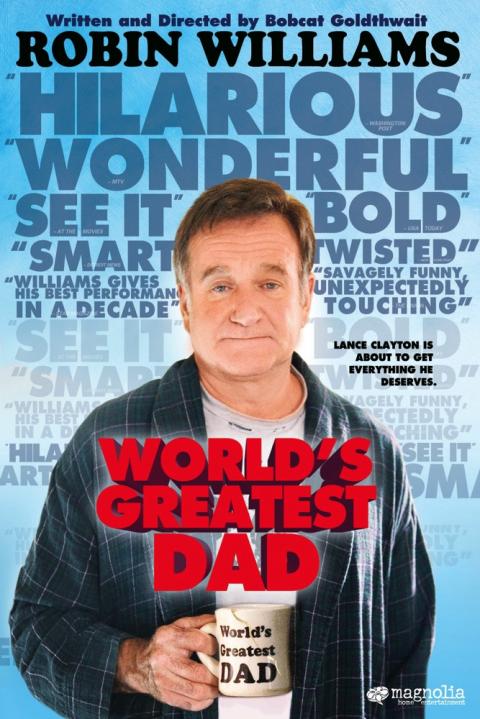
とても真っ黒なコメディだったよ。リチャード・ケリーがプロデューサーに名を連ねているけど、むしろウェス・アンダーソンの作品をさらに意地悪にして、サントラをブリティッシュ・ロックからAORに差し替えたらこうなるかな、といった感じの作品だった。
主人公のランスは人気作家になることを夢見る高校教師だったが今まで書いた小説はすべて出版社に拒絶され、高校で担当する詩のクラスも人気がなくて生徒がほとんどいないという有様だった。おまけに彼が一人で育てている息子のカイルは口の汚い問題児でランスに反抗的な態度をとってばかりで、病気といっていいくらいに性的なものに興味を持っていた。いちおうランスは同僚の教師とつきあっているものの、彼よりずっと人気のある別の教師に彼女をとられそうになり、自分のクラスは廃止されそうになり、カイルは特殊学級に入れられそうになるという最悪の状況になっていたある日、カイルが不慮の恥ずかしい事故で死亡してしまう。彼の死因を隠そうとしたランスは息子が自殺したことに見せかけ、即興で彼の遺書を書き上げる。ところがその遺書が公表されたことで高校ではカイルへの同情と人気が高まり、まるでカルト崇拝のようになってしまう。そして周囲にせがまれたランスは、カイルの「日記」を新たに書いて公表するのだが…というような話。
ランスを演じるロビン・ウィリアムズって映画では失敗作のほうが多い気がするけど、「フィッシャー・キング」とか「インソムニア」とかでたまに見事な演技を見せてくれてるわけで、この作品でもウソを心に抱えて生きる主人公を好演している。顔をクシャクシャにゆがめて嘆く姿とかは実のところキモいのだが、それがかえって役に深みを与えているかと。息子のカイルを演じるダリル・サバラは、「スパイキッズ」の弟がいつの間にか小太りのティーンになってたことに驚いたけど、変態のクソガキを熱演しているぞ。親に反抗的とはいえ学校で皆に人気があるわけでもなく、親と同様にルーザーであるところがポイント。この親子以外の登場人物は典型的なメガネっ娘やゴス娘とかで、みんな薄っぺらな性格しか持ってないんだけど、歌を多用した大げさな演出のおかげで、あくまでもサタイアの道具であることが明確にされるので物足りなさはなし。
監督のボブキャット・ゴールドスウェイトはウィリアムズとつきあいの長いコメディアンで、ニルヴァーナのカート・コベインとも親友だったそうな。それを知って理解したんだけど、この映画ってコベインとかマイケル・ジャクソンとかの有名人が死んだあとのカルト人気に対する痛烈な皮肉になってるんだよな。彼らが死んでから「彼は心が純粋な人だった」とか「俺は彼の1番のファンだぜ!」とか言っている人がいるけど、お前ら本当に彼らのこと分かってんのかよ、という皮肉が込められているという。ニルヴァーナのベースだったクリス・ノヴォセリックがチョイ役で出ているのもこれと関係しているのではないかと。
題材が題材だけにちょっと後味の悪いコメディではあるものの、笑えるところは笑えるし、上記のような皮肉も込められていてなかなか興味深い映画であった。
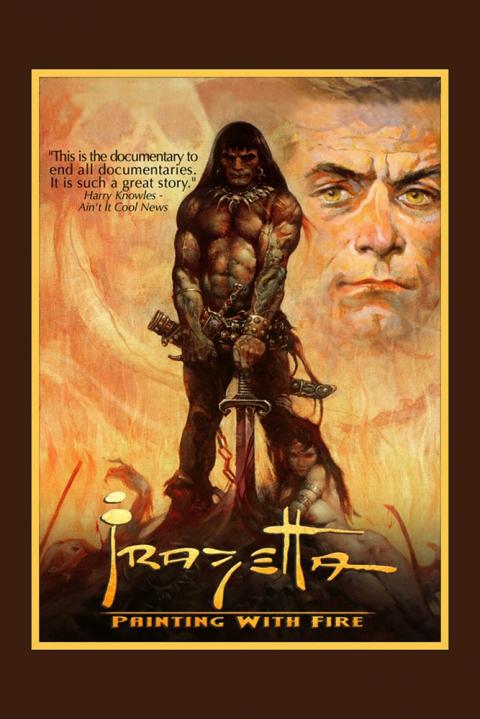
追悼記念としてフランク・フラゼッタのドキュメンタリーを観る。ブルックリンのタフな界隈で育ったフラゼッタは幼い時から天性の画力を発揮し、当初はコミック・アーティストとして動物漫画を描いたりアル・キャップのアシスタントを勤めたりしたのだが、50年代のコミックの衰退とともに業界を離れ、「マッド」誌に描いたリンゴ・スターの似顔絵がきっかけとなってハリウッド映画のポスターを手がけるようになり(この頃はカリカチュアが多かった)、それから「ターザン」や「コナン」などのペーパーバックの表紙を描くようになって多くのアーティストに影響を与える存在となっていく。彼って意外と多くのコミックを描いてるんですね。ペイント画も十分に躍動感があるけど、コミックではさらに動きが強調されていて俺はそっちのほうが好きかも。
若い頃はロバート・ミッチャムのごとき端正なルックスを誇り、その体は筋骨隆々としていて空手は黒帯、野球ではニューヨーク時代のジャイアンツから2度もスカウトを受け、でっかいバイクを乗り回し、カメラを500個も持っているカメラマンで、彫刻も手がけたというとにかく超人のような人物だったわけですよ。その一方では妻と子供たちを深く愛した家族思いの人であったことが語られていく(90歳を越えた母親も登場するぞ)。1990年代には病魔に襲われて鬱になったりしたらしいが、心臓発作により右手に痺れが残ったため左手で描くことを習得したという話には脱帽するしかない。作品は締め切り日の前夜に短時間で一気に描き上げるなんて話も面白かった。
ドキュメンタリーとしての作りは凡庸で、キャラクターを切り抜いたり後光を当てたりするようなエフェクトのかけかたには少し疑問が残るが、フラゼッタ本人および彼のアートが非常に魅力的であるために観ていて飽きがこない。またニール・アダムスやバーニー・ライトソン、ラルフ・バクシ、ジョン・ミリアス、ボー・デレクなどといった様々な分野の人たちにインタビューをしていて、フラゼッタのアートがいかに多くの人々に影響を与えたかがよく分かる内容になっている。あらためて彼の凄さを実感させてくれる作品であった。