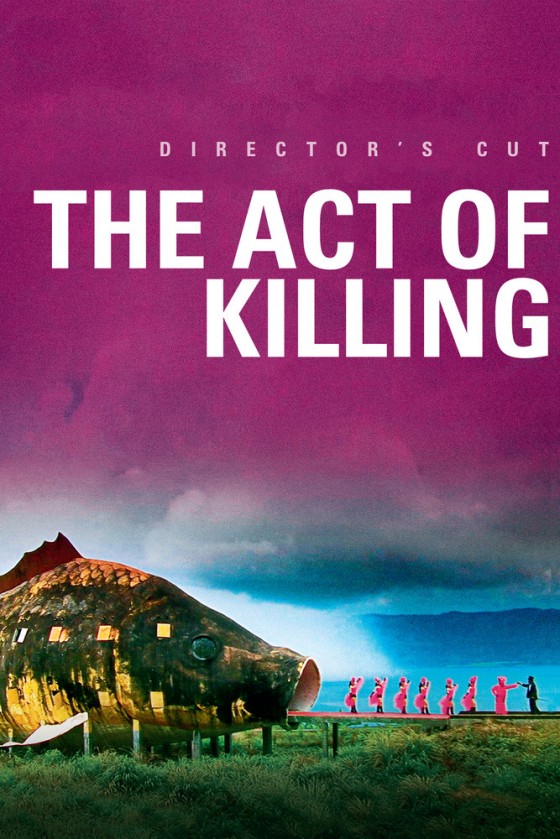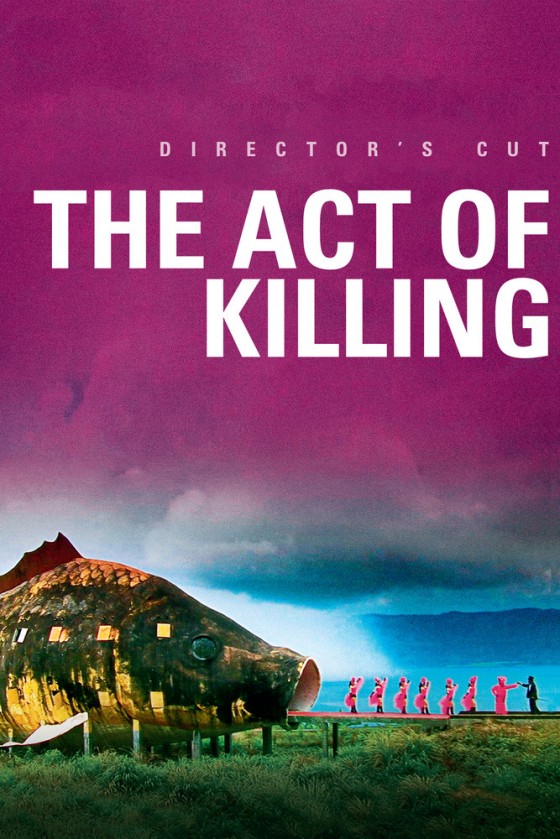
昨年公開されて絶賛と論議を呼んだジョシュア・オッペンハイマー監督のドキュメンタリー。プロデューサーにヴェルナー・ヘルツォークとエロール・モリスという巨匠が名を連ねているが、製作自体にはあまり関わってないみたい。122分のバージョンと159分のものがあって、後者を観たのだが、122分のほうにだけ使われてる映像もあるとか?
インドネシアで1965年に起きた軍事クーデターの結果として行なわれ、100万人もの共産主義者(中国系が多い)が殺されたという大量虐殺に関与したアンウォー・コンゴ(劇中ではずばり「処刑人」という肩書きで紹介される)を追ったもの。70を超えても高そうなシャツとスーツに身を包み、入れ歯を入念にチェックするアンウォーは北スマトラ州で映画館のチケットのダフ屋をしていたギャングの一員だったが、軍部が共産主義者の粛正にあたりギャングの手を借りたことから、彼らの虐殺に加担することとなりワイヤーを使った絞殺具で1000人もの共産主義者を殺したことを公言する(撲殺は血だらけになるから絞殺を好んだらしい)。
そのままギャングはパンチャシラ・ユースという数百万人規模の準軍事組織に組み込まれ、政権を支える存在として今日に至っている。彼らはマスコミや政権ともズブズブの関係であり、カメラの前で平然と華僑の店から金を巻き上げ、市民には賄賂を要求している。そして共産主義者の駆除に貢献したアンウォーのような処刑人は彼らにとって英雄であり、彼らを鼓舞する集会にギャング出身のアンウォーはよく招かれるのである(『「ギャング」というのは「自由人」という意味だよ』と政治家を含めた多くの人が語るのが印象的)。
このドキュメンタリーの最大の特徴は、この「残虐行為を行なった人たちが、そのまま現在でも権力の座についている」というところ。例えば第二次世界大戦とかベトナム戦争を扱ったドキュメンタリーだと、惨劇はあくまでも過去の出来事であり、それが回顧され、時には加害者と被害者が和解するというものが多いのだけど(ヘルツォークのこれとか)、この作品においては共産主義者への弾圧はまだ続いており、テレビ番組では若い女性キャスターが虐殺のことを当然の行為として言及し、アンウォーたちは自分たちの行なったことをむしろ誇らしげに若者へ語るのである。そんなアンウォーに対してオッペンハイマーが行なったのは、彼の虐殺行為を、彼の望む映画のスタイルで再現させることだった。
このため題名はつまり「殺人の行為」と「殺人の演技」という2つの意味を持つことになるわけだが、ギャング時代からハリウッド映画に憧れ、自分はシドニー・ポワチエに似ていると公言するアンウォーは往年のミュージカルや西部劇、ギャング映画のスタイルを踏襲し、自らも出演して殺戮の現場を再現していく。これらの再現において歴史的考証とかリアリティなどは二の次であり、加害者の役の人がいつの間にか被害者を演じてたりするわけだが、処刑人たちが尋問や処刑の方法について入念に説明したり、養父を殺害された男性が尋問される共産主義者を演じるにあたり、やがて現実と虚構(演技)の境界は溶けてなくなっていく。村の虐殺シーンにゲスト出演した政治家が、演技で「共産主義者どもをぶち殺せ!」などと叫んだ直後にオッペンハイマーに向かって「うちら本当はもっと人道的だからね!」などと注釈を入れる光景は筆舌に尽くし難い。
ちなみにアンウォーの片腕的存在としてハーマン(ヘルマン?)・コトというデブのチンピラが出て来るのだけど、ジャイアン的というか、ニック・フロストやジェフ・ガーリンあたりが演じそうなキャラでもう最高。年齢的に虐殺には関わっていないと思うが、女装して肉にかぶりつく入魂の演技を見せたりと、作品にものすごいアクセントを加えている。実生活でも「オラ金持ちになるだ!」と奮起して議員選挙に立候補するなど、彼がいなかったらもっと異なる作品になってったんじゃないかな。
そしてアンウォーと同様に虐殺に関わった旧友もまた撮影に参加するのだが、彼の場合はもっと「自分たちの行ないは冷酷であった」ということを自覚しており、このドキュメンタリーが世の中に出た時の影響を懸念している。その一方では「歴史というものは勝者によって書かれるものであり、我々はその勝者である」として自らの行いを正当化しようとしている。実際に処刑人の多くは精神に異常をきたすことがあると示唆されるのだが、アンウォーにとっての殺人の正当化の手段は、ギャング時代に観たハリウッド映画であった。アクション映画などを観て高揚したあとに、(酒やドラッグも加わって)殺害を行なうのである。
これらの演技を通じたアンウォーの心境の変化は劇中だといまいち汲み取りにくいところもあるのだけど(自責の念が完全に欠落しているので)、そこらへんについてはネット上におけるオッペンハイマーの一連のインタビューが参考になるかと。とはいえアンウォーも自分の行為を再考するようになり、衝撃的なラストシーンへとつながっていく。
これを観て単に「あーインドネシアって非道い国だなー」って考えることは容易だよ。エンドクレジットに載ってるスタッフの大半は、政府の迫害を恐れて「匿名さん」になっているし。ただここで描かれてることって、一国の出来事でなくもっと人間の根本的な悪というか不正義をさらけ出しているのだろう。そして我々はそれを過去のこととして切り捨てることもできず、その上に築かれた日常において幽霊たちと暮らさなければならないのである。