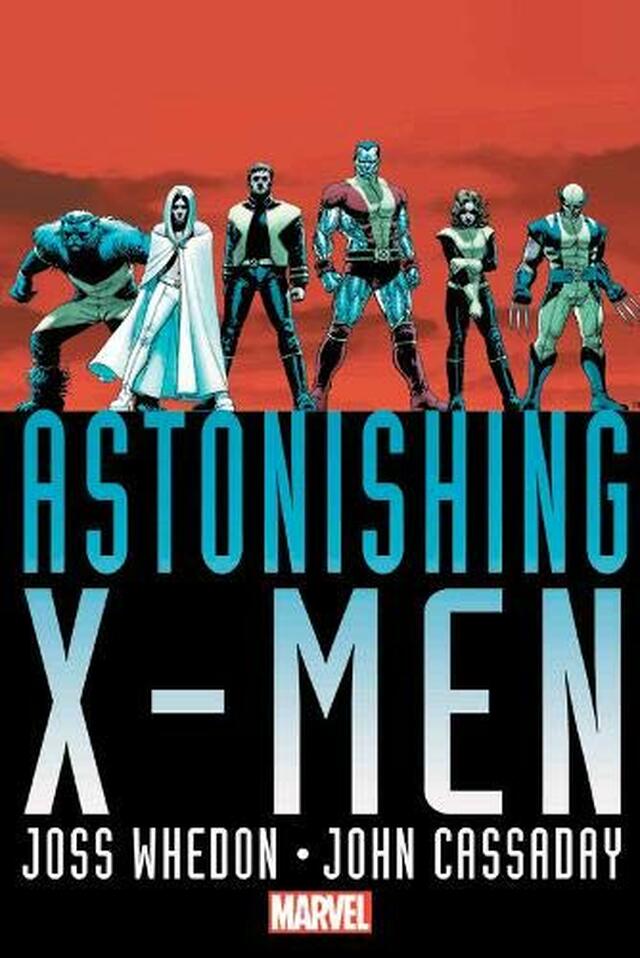アカデミー賞にもいろいろノミネートされて話題の作品。日本は7月公開かな。以下はネタバレ注意。
30歳になるキャシーはかつて医大にも通っていた前途有望な女性だったが、ドロップアウトしていまは実家で暮らし、コーヒーショップでダラダラ働いていた。しかし彼女には裏の顔があり、それはナイトクラブで酔った振りをして、彼女に言い寄って部屋に連れ込む男たちを逆に痛い目に遭わせることだった。周到な準備をして男たちに仕置きをしていくキャシー。いったい何が彼女にそのような行為をさせるのか…というあらすじ。
話が進むうちにキャシー自身でなく幼なじみの親友が大学で性的暴行を加えられたことが示唆され、それに対する復讐としてキャシーがビジランテ的行動をとっていることが明らかになってくるのだが、「Ms.45(天使の復讐)」みたいなバイオレンスものではなくて、武器も使わずにもっと個人的な辱めを加えていくといった感じ。彼女の復讐の対象は男性に限らなくて、事件を揉み消した学長や同級生たちにも及んでいく。
ここ最近のMeTooムーブメントを強く反映しているような内容で、まあ男性が観るといろいろ気まずい思いを抱くんじゃないだろうか。キャシーはいい年してパステルカラーのギャルっぽいファッションをしている人で、実家の部屋もお屋敷みたいな内装になってるわけだが、これ若い頃で彼女の時間が止まっていて、そのときから今まで彼女が物事を明らかにできなかったことを象徴してるのでしょうね。セットデザインといえば弁護士の家の花が枯れてるところも印象的だった。
監督のエメラルド・フィネルってこれが監督デビュー作だが、イギリスでは役者やってるほかに「キリング・イヴ」のショウランナーもやってた人だそうで、この作品の雰囲気もイギリスのドラマっぽかったかな。銃が出てこないところとか、キャシーと両親の小ぢんまりとした関係とか。
キャシー役のキャリー・マリガンはいま35歳だそうだが、キャシーの痛々しいファッションがよく似合っております。最初は観ていてドン引きするものの、やがて孤独な仕置人のコスチュームみたいに見えてくるから不思議。共演者がやけに豪華で、クランシー・ブラウンやアルフレッド・モリーナ、アリソン・ブリー、コニー・ブリトン、モリー・シャノンなんかが出ています。プロデューサーはマーゴ・ロビーだぞ。
観てスッキリするかというと全くそんなことはない作品なのだけど、時代をうまく反映した作品だなとは思う。モヤモヤは残るけどね。