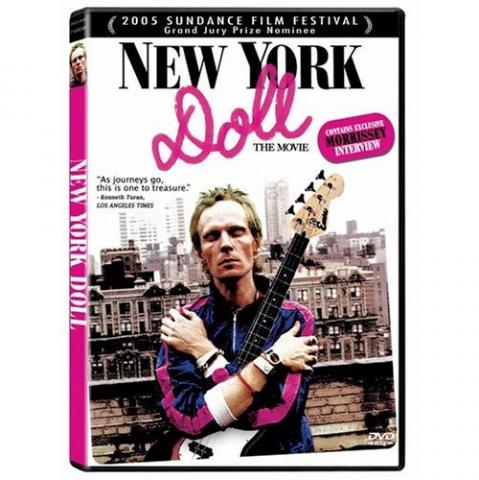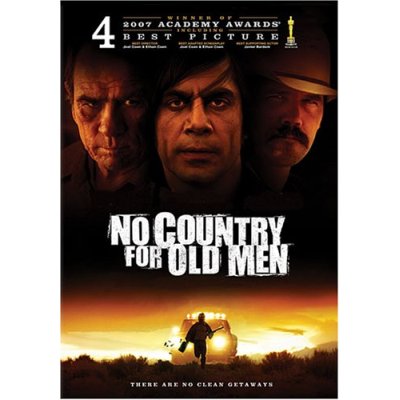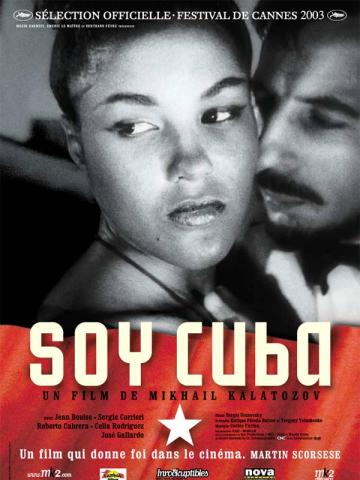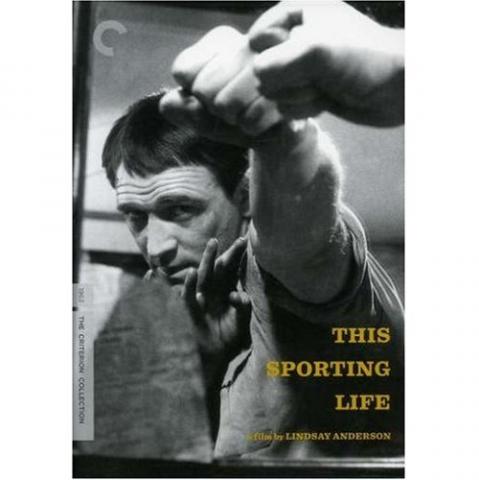
「オー!ラッキーマン」のリンゼイ・アンダーソン監督による1963年の映画「孤独の報酬」(This Sporting Life)を観た。
主人公のフランクは炭坑夫だったが、街でラグビーのチームに出会ったことから入団テストに志願し、持ち前の獰猛さをもってテストに合格、スター選手の仲間入りをすることになる。その一方で彼は下宿の大家で、子持ちの未亡人であるマーガレットに恋をしており、いろいろ言い寄ろうとするが彼女はなかなかフランクに心を開いてくれない。そんなうちに彼は試合で殴られて前歯を折る大ケガをし、選手としての活躍にも陰りが見え始め、ゆっくりと転落の道を辿っていくのだった…。というのがまあ大まかな話。
あまりにも愚直であるばかりに好きな女性には強引に言い寄ることしかできず、チームのオーナーたちには「筋肉バカ」としか見なされない男の悲哀をうまく描いた作品。ガタイのいいマーロン・ブランドといった感じで主人公のフランクを演じるのはリチャード・ハリス。この人の作品って「ハリー・ポッター」くらいしか観たことがなかったんだけど、こんな屈折した悩みを持った男を演じられる名優だったんですね。あと初代ドクター・フーことウィリアム・ハートネルも脇役で出てるぞ。
尺が134分と長いために冗長なメロドラマのように感じられるところもあり、時には主人公の傲慢さが鼻につくところもあるものの、過去と現在の場面が交差してストーリーが始まる編集のテクニックは興味深いし、白黒の画面のなかで男たちが泥にまみれるラグビーの試合の描写などもよく出来ている。60年代のイギリスの労働者階級を如実に表した佳作といったところか。