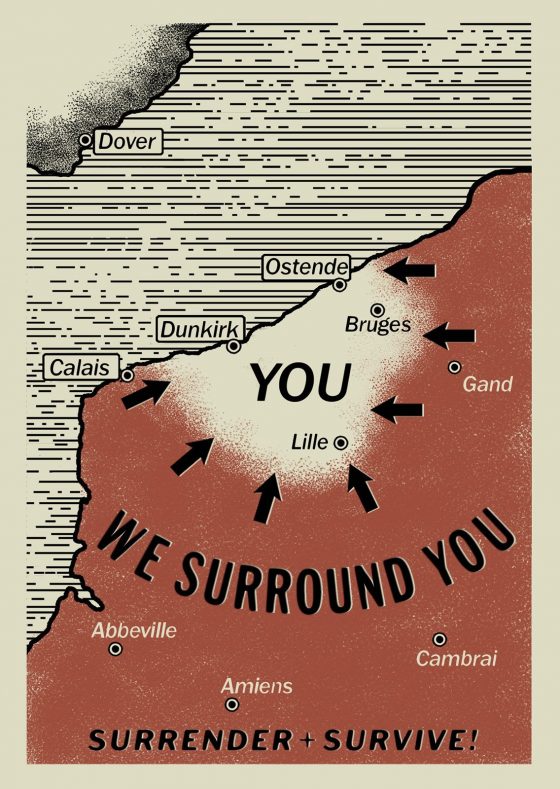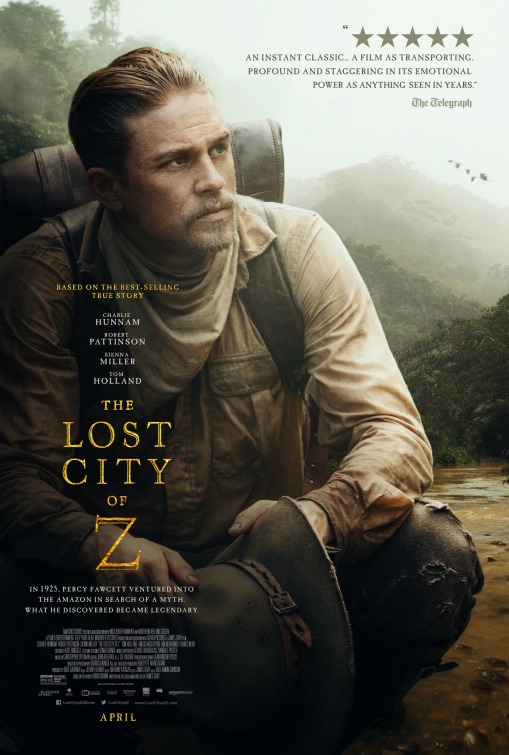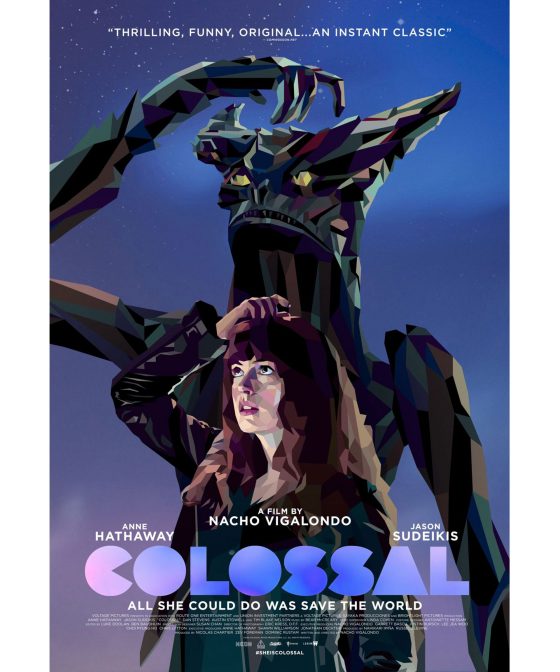「フランクリン&バッシュ」や「シリコン・バレー」などで日本でもお馴染み(?)のコメディアン、クメイル・ナンジアーニの伝記的映画。奥さんのエミリーとの出会いを描いたもので、脚本も二人が執筆したものになっている。
シカゴに住むパキスタン系のクメイルはウーバーの運転手をしながらコメディクラブに出演しているコメディアンで、ある晩にエミリーと知り合って二人はすぐに恋に落ちる。しかし彼の両親は伝統的なムスリム教徒で、パキスタンの伝統にのっとってパキスタン系の女性とクメイルを結婚させようと躍起であり、さまざまな女性をクメイルに紹介していた。このためクメイルは白人のエミリーのことを両親に紹介できず、それがたたって二人の仲は険悪なものになってしまう。そんなときにエミリーが謎の疾患によって昏睡状態になってしまい、クメイルは彼女の看病にやってきたエミリーの両親に出会うことになる…というあらすじ。
監督は「ザ・ステイト」出身のコメディアンのマイケル・ショワルターだが、プロデューサーをジャド・アパトウが務めていて、全体的な雰囲気もアパトウ作品っぽいかな。ドラマとコメディの比率が8:2くらいなとことか、微妙に必要以上に尺が長いところとか。
クメイルとエミリーは出会ったその晩にヤッてしまうくらいの相性なのですが、クメイルはエミリーを自室に連れ込むなり「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」を見せたり、3回目のデートでは「怪人ドクター・ファイブス」を見せつけるという筋金入りのオタク。そんな趣味についてこれる女性がいるかよ!とは思うがまあ実際にあったことなんだろうなあ。その一方でそれなりに事実に脚色がされていて、クメイルの両親は実際もっと話がわかる人たちだったみたい。
話の前半でエミリーが昏睡状態になって、そのあとの話はエミリーの両親とクメイルが互いに打ち解けていく過程が中心になっていく。コメディアンとしてのキャリアを築こうとするクメイルの奮闘も並行して描かれるが、感情的になってステージ上で全然笑えないセットを披露してしまうくだりはね、他の映画でもたくさん見てきた展開なのでクリーシェすぎたです。
クメイルを演じるのはクメイル自身だが、エミリーはゾーイ・カザンが演じている。エミリーの両親をレイ・ロマーノとホリー・ハンターというベテラン勢が演じていて、最初はクメイルのことを敵視しているハンターの演技がすごく良かったな。クメイル・ナンジアーニのコメディって、どことなく無感情というか突き放した感じがあって個人的にはそんなに好きではなかったけど、この作品では激昂して暴れるシーンとかもあって結構面白かったです。
なんとなく先が読める予定調和の話ではあるし、スタンダップコメディの世界とかパキスタン系アメリカ人の結婚事情なんてのは日本人にはとっつきにくい題材かもしれないが、ほんわりとしたロマンティック・コメディであって結構楽しめる作品でしたよ。「ベイビードライバー」と並んでこの夏に高評価を受けた作品であるというのも納得。