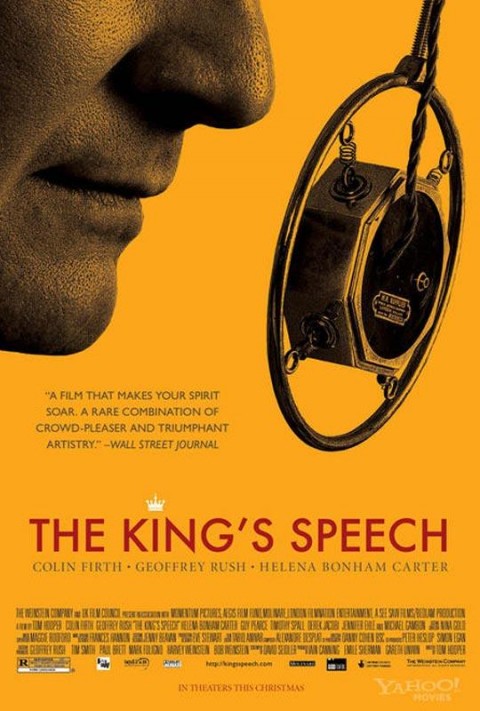出張帰りの飛行機のなかでは映画を4つ観たのだよ:
「ガリバー旅行記」
ジャック・ブラックは嫌いじゃないんだけどね。こういう凡作でありきたりな役ばかり演じてるとそろそろ飽きられるんじゃないかと。意中の人がアマンダ・ピートだってのもいいかげん無理があるよな。せっかく脇役にクリス・オダウドとかキャサリン・テイトとか使ってんのにこの出来とは勿体ない。特に後者は殆どセリフがなかったような。あとジェイソン・シーゲルはもうちょっと痩せたほうがいいと思う。
「ファースター 怒りの銃弾」
むかし銀行強盗をしたあとに襲撃され、兄を殺され金を奪われたザ・ロック様が、出所後に自分を襲撃した連中に復讐していくアクション。でも主人公はあまり復讐心に燃えてなくて困惑した顔で人を殺してるし、復讐される側もみんな「あーついにこの時がきたかー。」といった感じで半ば諦めてて、まっとうなバトルは展開されない。というか主人公、刺し殺したはずの相手が蘇生したので病院まで行ってさらに撃ち殺すというのはなんか情けないぞ。これに定年間近の警部とか動機不明の殺し屋とかが加わり、伏線もないまま腹の立つような展開が待つラストを迎えていた。何も観る価値がない駄作。
「ナルニア国物語/第3章」
おれ小中学生のときに原作を全部読んだはずなのだけど、この話の内容は完全に忘れてしまっていたよ。マイケル・アプテッドが監督してるのに子供たちよりもCGにばかり焦点が当てられてしまっているのが残念。キリスト教徒をターゲットにした映画なので、アスランが話したりするたびに「これはキリストのどういうアレゴリーなんだ?」と変に穿った見方をしてしまった。
「デビルクエスト」
ニコラス・ケイジがまた女性に暴力を振るう映画。こないだDV容疑で逮捕されたことを考えるとあまり笑えんな。中世の騎士が魔女を檻に入れて運ぶだけの内容で、照明は単調だしCGはゲームなみだし何もいいところなし。こんなの日本で劇場公開するんだったら他にもっといい映画が山ほどあるだろうに!ケイジはもう真面目な映画に出ない方がいいんじゃないだろか。
半ば寝ながらでも話を追っていける映画ばかり選んだら、結局のところダメ映画ばかりになってしまった。こんなんだったら「ブルー・バレンタイン」でも観とけばよかったな。