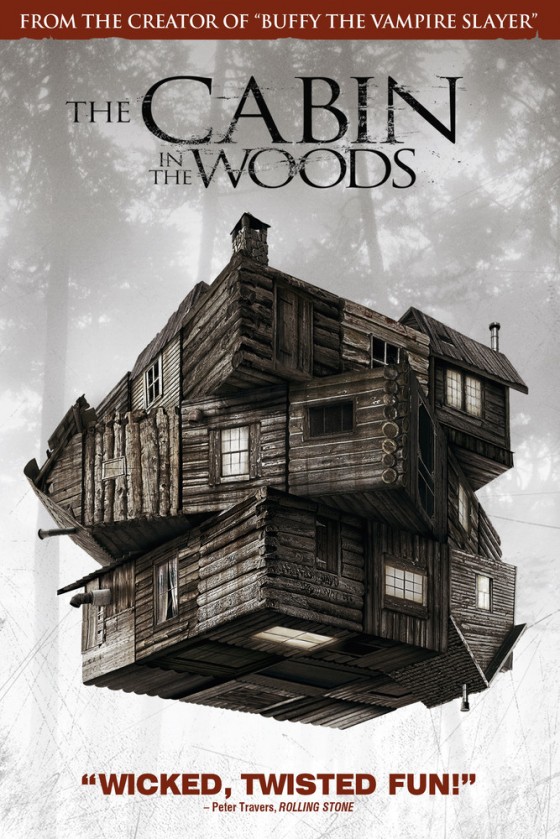
「アベンジャーズ」で今をときめくジョス・ウィードンが脚本と製作を担当した作品で、監督は「クローバーフィールド」の脚本家のドリュー・ゴダード。2009年に撮影したのがいろいろあって公開が今年まで公開が遅れたらしい。
大学生のダナとその友人のジュールズ、およびその仲間たち計5人の男女が、田舎の山奥にある山小屋へキャンプに行くところから話は始まる。森のなかの山小屋に到着した彼らは湖で泳いだりと楽しいひとときを過ごすものの、やがて周りで奇妙な現象が起きることに気づく。そして彼らは何者かに監視されていたのだった…というようなプロット。
これ以上の設定をバラすと話がいっぺんにつまらなくなるので細かい説明は省くが、要するにホラー映画をとてもメタな視点から語った異色作になっている。典型的なティーン向けホラーを脱構築しているというか。メタな様子があるホラー映画というと「スクリーム」が以前にあったが、あれよりもさらに奇妙なプロットのツイストが加わっている感じ。また同じティーンの主人公たちでも、ケヴィン・ウィリアムソンよりもジョス・ウィードンの作品のほうが活発でいいですね。今回の5人はやはり「スクービー・ドゥ」の登場人物をモデルにしてるんだろうか。
キャストは雷神ソーことクリス・ヘムズワースが出演しているほか、中間管理職的な役をブラッドリー・ウィットフォードが好演。最後にはあのお方もカメオ出演しているぞ。いちばんのめっけものは主人公のダナを演じるクリステン・コノリーという女優で、1980年生まれとは思えない童顔でコケティッシュなスクリーム・クイーンぶりを見せつけてくれるぞ。
ホラーかと言うとそうでもないし、かといってSFやコメディというわけでもないし、なかなか一筋縄ではいかない映画だけに観る人を選ぶかもしれないが、こういう作品を作ってしまえることは凄いと思いますよ。何の前知識も持たずに観に行って、目の前で起きる怒濤の展開に呆気にとられるべき映画かと。



