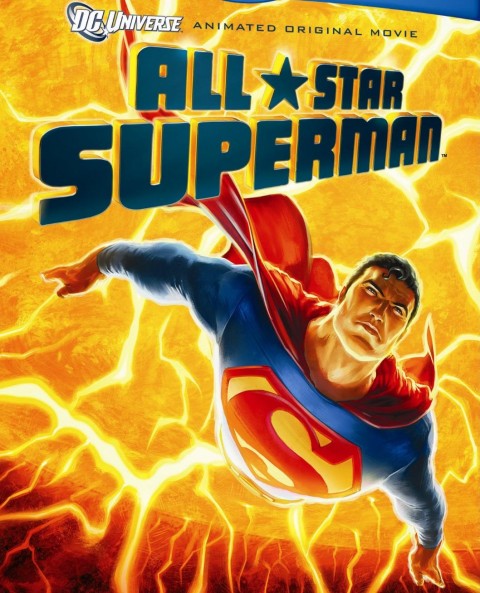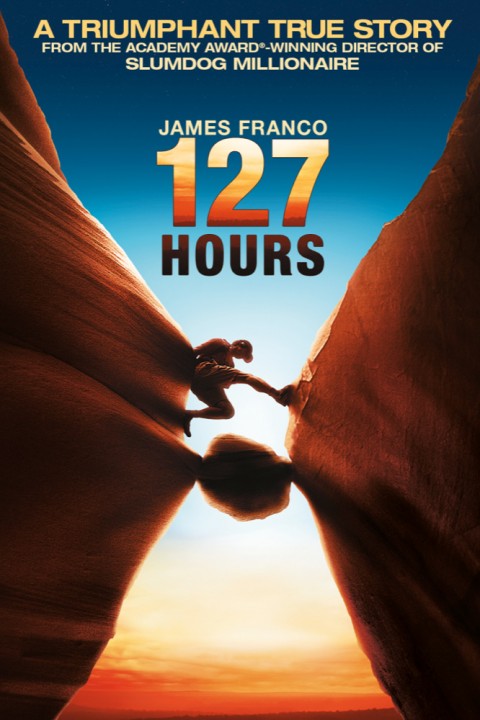
最初に言っとくとグロ注意。切断シーンはやはり痛いよ痛いよ痛いよ。デートで観たりするとちょっとしんどいことになるかも。
これを観る人の殆どがストーリーの展開および結末を事前に知っているだろうし、場所の移動などは皆無に等しい内容でありながら(だって人が5日間岩のあいだに閉じ込められる話だぜ?)、映画としてここまで楽しめる出来にしてしまった手腕はやはり凄いなあと。普通だったらどこかのケーブル局がTVムービー化する程度だったろうに。
以前にも書いたがダニー・ボイルっていま活躍中の映画監督のなかでも抜群の映像センスを持った人で、ミュージック・クリップ出身の監督たちとも違った独特のスタイルを誇っていると思うんだけど、前作「スラムドッグ・ミリオネア」ではその映像美が行き着くところまで行ってしまったような気がしたんだよな。そして今作も基本的にはそのスタイルが踏襲されているんだけど、話の展開自体はとても地味なので、それを映像美が補うことでいい感じの相乗効果が生まれている。自分の尿を飲むシーンをスタイリッシュに描ける監督というのはそういないだろう。
自分の腕を岩に挟まれて身動きできなくなった主人公の苦境と、彼の回想や妄想がカットバックする作りは「トレインスポッティング」でレントン君がベッドで寝込んでるシーンの雰囲気に近いかな。狭い岩間と、そこから見える頭上の青い空との対比などが非常に効果的。話を通じて主人公が大きく成長するような話ではないので「スラムドッグ」に比べると弱冠物足りない感じもするが、とても良く出来た作品ですよ。