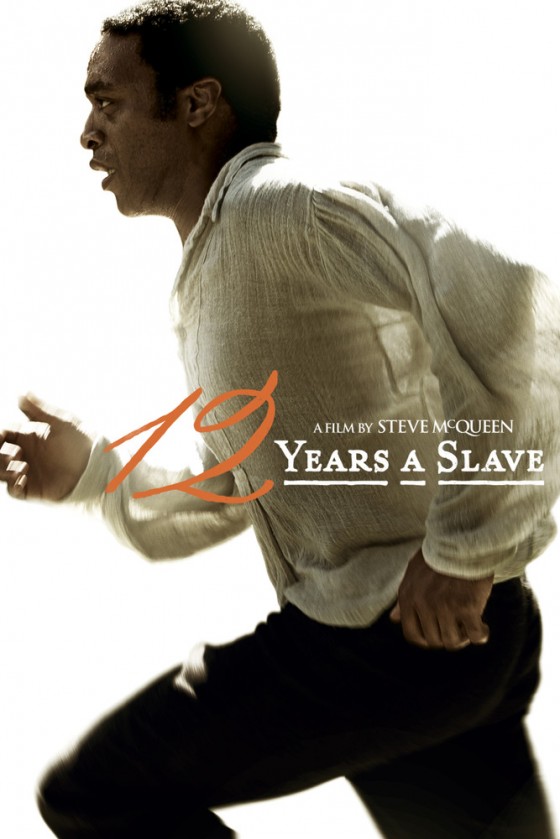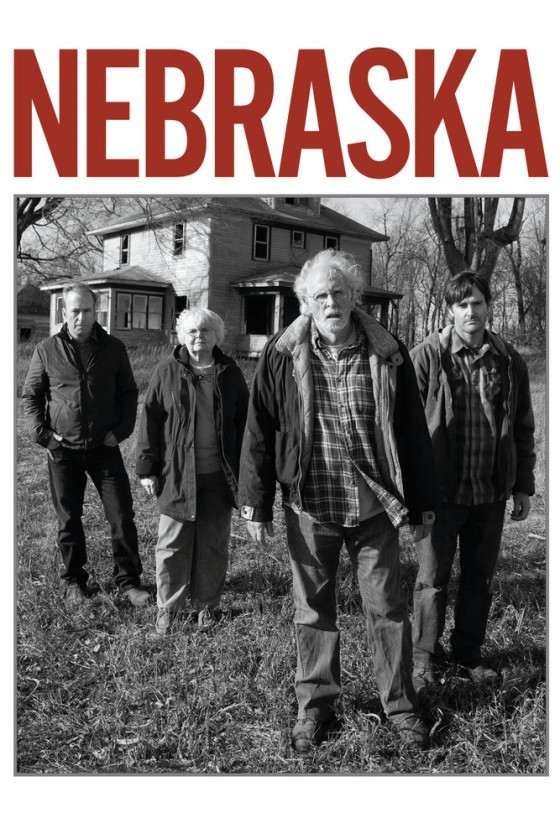日本(だよね?)を舞台にした「47 RONIN」が批評的にも興行的にも壊滅的な結果であったのが記憶に新しいキアヌ・リーブスだが、実はアジアチックな映画に昨年もう1つ出ていて、さらにこちらでは初監督まで務めている。舞台は中国、セリフも殆ど中国語という完全な中国映画なのだが、これってキアヌが「僕が出演と監督やるから映画を作らせてよ」と中国資本にアプローチしたのかな。結果としてはやはりトンデモな作品になっていて、以後はみっちりネタバレしながら書くのでご注意ください:
タイガー・チェンはリンコン太極拳を学ぶ若者で、配達業のバイトをしながらも老師の唯一の弟子として修行に励んでいた。太極拳は精神的なものだと老師に説かれるものの、その可能性を世に知らしめたいと思ったタイガーは異種格闘技のトーナメントへと出場する。太極拳ってゆっくり動く体操のようなイメージがあるけど、彼のリンコン太極拳はれっきとした武術であるらしい。そして初戦を勝利で飾ったタイガーは、その格闘スタイルを謎の大富豪ドナカ・マーク(キアヌだよ)に目をつけられる。
ドナカは香港で闇の格闘技場を運営しており、そこでの究極の試合は選手の生死をかけて戦われるものであった。彼の行いは中国警察にも不審に思われており、覆面捜査官が選手として内部に潜り込んでいたものの、負けた選手を殺めるのを拒んだために、逆にドナカによって刺殺されていた。なおドナカは負けた選手を始末するときにマスクを被るのだが、着てる服は一緒なので正体がバレバレである。何のためのマスクなんだ…。
ちなみにこの映画にふんだんに出てくる格闘シーン、素人目にはそれなりに迫力があって役者もよく動いているんだけど、どうもカット割りがやたら多くて「カットの合間に動きを修正してるよね?」と思わせてしまうのが勿体ない。もっと引きの画で長まわしにしてくれても良かったのに。あと主人公のパンチに迫力が無いような。
そしてドナカの「うちで警備の仕事をしない?」という誘いに興味をもったタイガーは、ドナカの部下の車に乗って彼のもとへと向かう。香港まで行くことを知らずに、空港で「どこへ俺を連れて行くんだ?」と驚くシーンがあるんだが、中国本土の人ってそんな容易に香港へ行けるんだっけ?税関は普通に彼を通していたぞ。
そしてドナカの会社についたタイガーは、だだっ広い部屋において何者かに襲われ、驚きながらも彼を撃破する。この「面接」をパスした彼は闇の格闘技場で戦うようドナカに誘われるが、即答はできなかった。しかし老師の寺院が安全基準を満たしていないために取り壊しの危機に面していることを知ると、その修繕費用を稼ぐためにタイガーはドナカのもとで戦う決意をする。この寺院の危機ってドナカの手回しかと思ってたが、どうも全くの偶然だったらしい。というか600年の伝統を誇る寺院の修繕費って自治体とから出ないんだろうか?
格闘技場では連戦を重ね、賞金を手にして羽振りが良くなっていくタイガー。両親にも洗濯機や車とかを買ってあげたりしてるんだが、それより寺院の修繕が先ではないのか?また彼は格闘技場でスキルを憶えるにつれてダークサイドに堕ちていき、表舞台の異種格闘技戦でもエゲツない戦いをするようになる。このとき着ている服が白から黒になるというのがね、実に分かりやすい図式になってますね。
しかしそのエゲツなさが災いして老師とケンカしたうえに当局に嫌われ、寺院の取り壊しはそのまま行なわれることに。それでもダークサイドに惹かれたタイガーはズルズルと格闘を続けていく。しかしこの作品、主人公が戦いを続ける理由がなんか希薄なのだ。トーナメントで太極拳をアピールするわけでもないし、金があっても寺院が救えたわけじゃないし。親兄弟の仇とか、難病の妹とかいった理由をつけてもバチはあたらなかったと思うぞ。
そんなタイガーに、ドナカを追う女刑事が接触し、タイガーは調査に協力することに。そしてついに彼は、生死をかけた決戦に向かう。そして試合前、会場に集まった怪しい客たちの前に披露されるのは何とタイガーの伝記映像!幼少の頃の映像に加えて、いかに彼が最強の戦士になっていったかが語られ、そこまでにしとけば良かったのに、彼がダークサイドに堕ちてエゲツない戦士になったことまでが丁寧にも説明される!これって風俗嬢に身の落ちぶれ方を説教するようなもので、これを見て目の覚めない奴はいないと思うのだが、何がしたいんだキアヌ。
そしてついに登場したタイガーの決戦の相手、それは特別出演した「ザ・レイド」のイコ・ウワイス!太極拳とインドネシアのシラットの熱い戦いが見られるかと思うと期待はいやがうえにも高まるのですが、さっきの映像を観てダークサイドから醒めたタイガーは「俺はお前とは戦わん!」と対戦を拒否!代わりにカメラを通じて試合を観ている客たちに向かって「俺は、お前らと戦う!」と言い放つのですが、目の前にいる敵から逃げ回りながら言っても全然説得力ないぞ。そんなうちに警察が会場になだれこみ、イコ・ウワイスとの一戦はお流れに。ドナカだけは会場から真っ先に逃げるのだが、泳いで本土まで行くたくましさ。ボートくらい用意しとけよ。
こうして闇の格闘技場を運営していた一味は壊滅し、老師のいる道場へと戻るタイガー。しかしそこで彼を待ち受けていたのはドナカだった。お前の命はもらった!とばかりに襲ってくるドナカ。悪役をアメリカ人とか日本人とか中国人官僚とかにせず、キアヌ本人にしたのは政治的なしがらみとかが出なくて巧いとは思うが、キアヌの格闘シーンがいちばんフェイクっぽく見えるのが興醒めである。だからイコ・ウワイスとの一戦で〆ておけば…。
しかしダークサイドから脱して太極拳をマスターしたタイガーにとって、ドナカはもはや敵ではなかった。タイガーの波動拳(いやホントに)を受けて絶命するドナカ。最後に「お前ならやってくれると思ったぜ…」と捨て台詞を吐くのだが、タイガーは結局ダークサイドに堕ちなかったし、自分の組織は壊滅してるし、全く自分の思った通りになってないじゃん!いったい何がしたかったんだキアヌ。
というわけで、なんかベタな展開の続く作品でありました。出来の悪い少年マンガを読んでいるような感じであったよ。これでも何故かアメリカでは「47 RONIN」より評判が良かったんだよなあ。俺キアヌ・リーブスは決して嫌いな役者ではないのですが、とりあえず監督とか製作からは手を引いて、才能ある監督のもとで役者に徹したほうが良いのではないかと、老婆心ながら思ってしまうのです。