
ニコラス・ウィンディング・レフンが「ドライヴ」に続いてライアン・ゴズリングと組んで作った新作。とってもバイオレントな内容なので、「ドライヴ」みたいにクールな内容を期待してデートで観たりすると後悔すると思う。
舞台となるのはタイのバンコク。そこでムエタイのジムを経営するアメリカ人のビリーとジュリアンの兄弟は裏で麻薬の密輸に手を染めていたが、ある晩にビリーが未成年の少女を強姦して殺してしまう。この事件は「復讐の天使」ことチャン警部によって法の外で裁かれ、少女の父によってビリーは殺害されてしまうのだが、物事の顛末を知ったジュリアンはさらなる報復を望まなかった。しかし2人の母であるクリスタルが事件を知ってタイを訪れ、ビリーの復讐を遂げるようジュリアンに命じる。これを渋るジュリアンだったが彼の手下たちが少女の父親を殺害、さらにチャン警部の殺害も計画するが返り討ちに遭ってしまう。そしてここに双方による血で血を洗う復讐劇の火ぶたが切って落とされるのだった…というストーリー。
トレーラーを観たときはマーシャルアーツ系の映画かな、と思っていたのだが完全なサスペンスというかスプラッターっぽい話でありました。タイの暗黒街を背景に、やられたらやり返すといった展開で人がバンバン死ぬ内容になっております。タイには売春婦と悪徳警官しかいないような描かれ方をしているのだが、いいのかこれ。あと「ドライヴ」同様に女性への暴力描写がちょっと気になりましたね。
ライアン・ゴズリングは「ドライヴ」以上に無口なキャラクターを演じていて、それなりのサイコ君であることが示唆されるものの、あくまでもビリーの不祥事を始末し、一家の主である母親(二の腕が立派なクリスティン・スコット・トーマス)のワガママに振り回される哀れな役回りを演じております。むしろ話の中心人物はウィタヤー・パーンシーガーム演じるチャン警部で、タイトルの「GOD」は彼のことを指しているらしいが、全くもって許したりはせず、ナベからナタを駆使して相手をフルボッコにし、しまいにはカラオケで一曲歌うという全能っぷり。こういうのは西洋人による東洋へのリスペクト感が表れているのかなあ。
「ドライヴ」で主人公がトンカチもって乗り込むナイトクラブのシーンが延々と続く内容というか、なんか極端な展開がずっと続くのでカタルシスなどは全く得られず、本国などではいろいろ酷評されたわけだが、かといって決して悪い作品というわけでもない。ガスパー・ノエに影響されたというタイの夜景やナイトクラブの映像はスタイリッシュで非常に美しいし、「ドライヴ」のシンセポップに代わってジョン・カーペンターばりの重厚なシンセミュージックが全編に渡って効果的に用いられ、とても印象的な出来に仕上がっている。ストーリーが「なんじゃあこりゃ?」なのが問題なわけで。
なんかこの作品で行きつくところまで行ってしまった感のあるニコラス・ウィンディング・レフンだが、次はどうするんだろうね?一説によるとイギリスのカルトコミック「Button Man」の映画化を企画しているらしいが…。
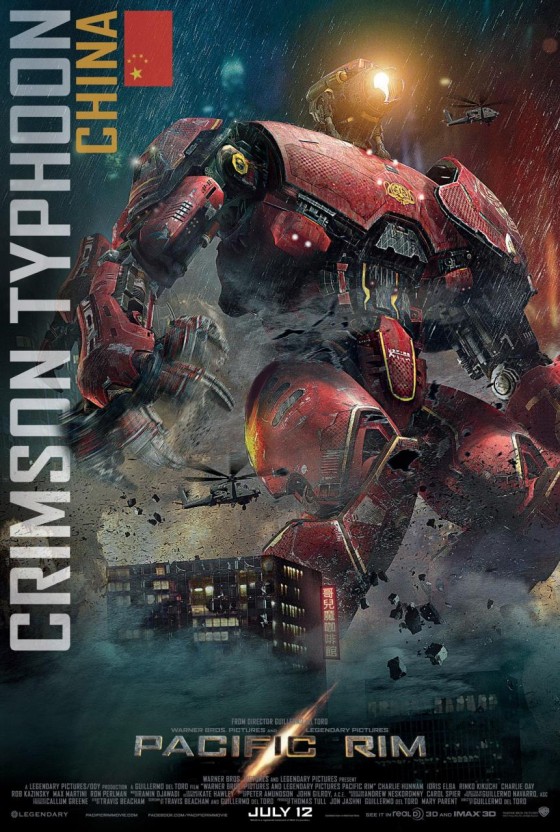
 ダニー・ボイルの新作。去年のロンドン・オリンピックの前後に製作したものらしい。以後ネタバレ注意な。
ダニー・ボイルの新作。去年のロンドン・オリンピックの前後に製作したものらしい。以後ネタバレ注意な。