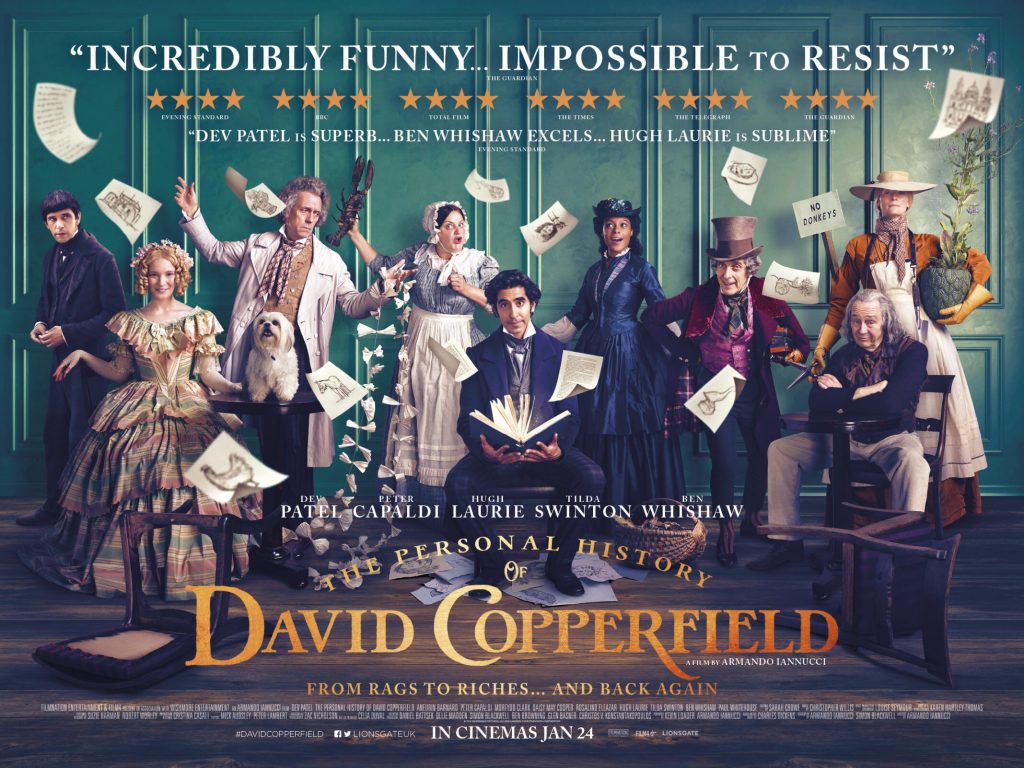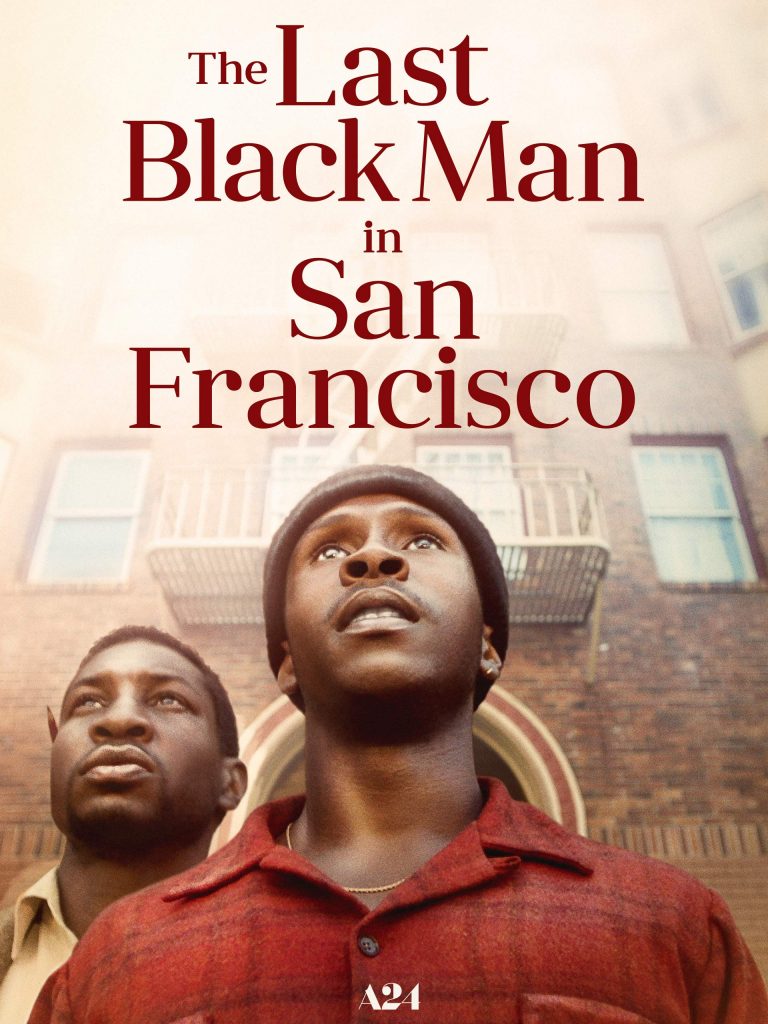鬼才(変人)ヴェルナー・ヘルツォークがいつの間にか日本で撮影していた映画で、アメリカのマイナーな配信サービスMUBIでプレミア公開されてたのを視聴。
話の主人公となるのは「レンタル家族」サービスを営む「ファミリーロマンス社」の社長である石井祐一。これ実在する会社の実在する社長で、以前にはコナン・オブライエンが日本で番組撮影したときにも登場してたみたい。この会社は社員を「代役の家族」として貸し出し、その社長や社員は顧客の要望に応じて様々な役を演じていく。
話の中心になるのは、父親がいない、まひろという名の少女の父親を石井が演じるパートで、石井と少女のやりとり、およびまひろの母親とのやりとりが作品を通じて描かれている。それに加えて石井が演じるのが、「ミスをした人」の代わりに上司に怒られる役とか、アイドル気取りの女性を歌舞伎町で撮影するカメラ小僧など。
家族代行サービスを営む人、という点ではヨルゴス・ランティモスの「ALPS」に設定が似てなくもないが、あれよりはもっと通俗的な役をロマンス社の社員が演じてるかな。いちど宝くじで大金を当てた女性が、あの感動が忘れられないとして、再び当選のお知らせを知らせる役を石井に頼むくだりは少しファンタジーっぽくて面白かった。
実在する会社の実在する社長を追った物語、という内容からこれをドキュメンタリーだと思い込んだ批評家が海外にはいたらしいが、ヘルツォークによるとすべて彼が書いた脚本が存在するフィクションであるらしい。まあ彼は普通のドキュメンタリーにも平気で脚色(本人曰く「イルミネート」)を持ち込む人なので、フィクションなのかドキュメンタリーなのか詮索するのも野暮ですが。
ただしヘルツォークは大まかな設定を書いたのみで、細かいセリフは出演者のアドリブなんだとか。彼自身は撮影監督もやっていて、ゲリラ撮影用の小さいカメラを持って役者に肉薄し、日本語は分からないものの良い演技が撮れたと感じたらその場でOKを出していたらしい。つまり役者が何を言ってるか分からないままでOK出してたみたい。77歳にもなってこんな撮影をしてるのはヘルツォークくらいのものだろう。自然の描写も彼が撮影ということで流石に美しいですよ。
ロマンス社に依頼をしてくる人たちもみんな役者(社の社員か?)が演じているのだが、みんな演技がヘタなのが逆にリアリティさを増しているというか。その一方で石井社長だけが口数豊かに業務をこなしていくあたりが、詐欺師ベテランっぷりを発揮していました。また、まひろの母親はデカい家に住む金持ちという設定なのだが、その家がどうも「例のプール」があることで知られるスタジオで撮影したものらしく、プールも一瞬ながらしっかり出てました。「例のプール」はAV撮影だけでなくヴェルナー・ヘルツォーク作品のロケ地にもなったんだよ!
このレンタル社員、今は亡き(あるいは不在の)人の代わりとなって残された家族とやりとりするさまは現代のイタコっぽいかな、と思ってたら、石井がまひろの母親とともに青森(?)までイタコに会いに行く場面が突然出てきて驚きました。みんなイタコの口寄せを黙って聞いてるだけなのだが、口寄せの最中に電話がかかってきたため、口で故人の言葉を語りながら、手で電話対応するイタコというのは初めてみました。あれトランス状態になるわけではないのですね。
ヘルツォーク曰く、この世におけるフェイクなシチュエーションでの感情的なやりとりを映したかったらしいが、まああまりそういうシーンはないです。歌舞伎町や「変なホテル」がロケ地に選ばれてるあたりからも、いかにも外国人が好きそうな日本の文化や場所が出てくるな、といった感じ。だからレンタル家族も珍しいものだとして映画化したのかもしれないが、日本人から観るとちょっと違和感を抱かずにはいられなかったな。
面白いかというと必ずしもそうではない作品だけど、ヴェルナー・ヘルツォークが日本で撮影したという点では非常に価値がある逸品ではないかと。